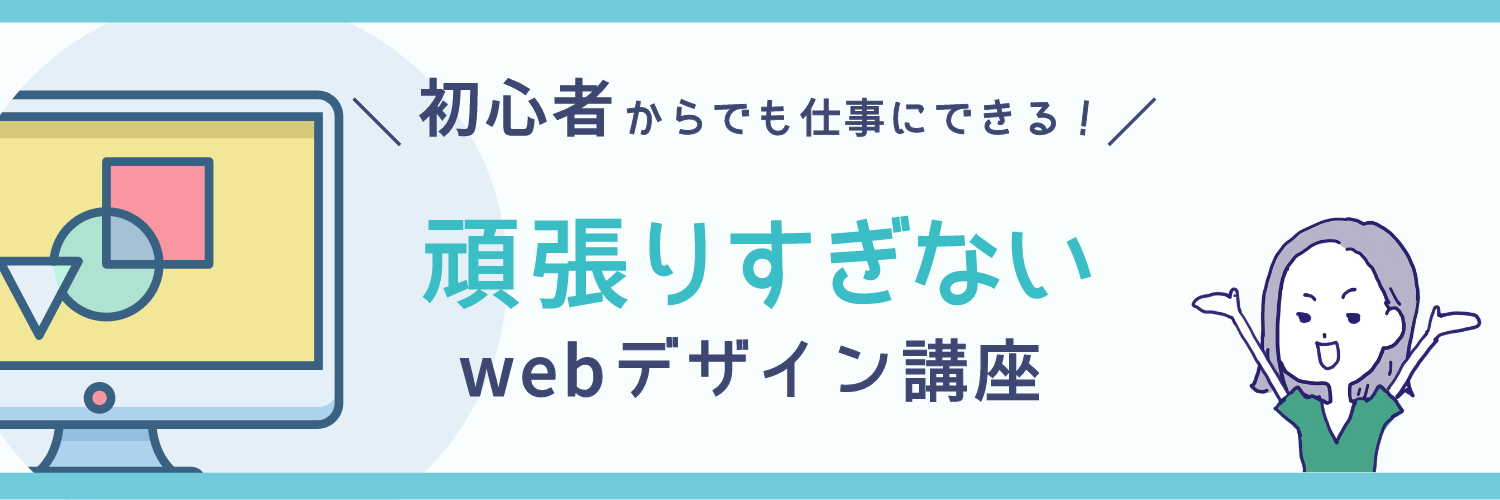こんにちは。
フリーランスデザイナーのちえみです。
webデザイナーになろう!と決意したものの、どうやってスキルを身につけたら良いのか分からず立ち止まっていませんか?
デザインのスキルを身につけるには学習による知識習得と実践数を増やしていくのがイチバンです。
しかし、いざ勉強しようと思っても、今はYouTubeなどで無料の講座動画があったり様々な会社が運営しているデザインスクールがあったりと、良くも悪くも選択肢が多いですよね。
独学だと「これであっているのだろうか?」「こんな時はどうするのが良いのか?」など1人では解決できない悩みが出てきて勉強が止まってしまうこともあります。
かといってスクールは種類が多く、自分に合っていないスクールに入ってしまうと時間とお金を無駄にしてしまうことも。
だから、どこで学ぶのが良いのか判断できなくて学べずに時間だけが過ぎてしまう…。
そこで、現役デザイナーの私が実際に試した経験をもとに初学者にオススメの学習方法をご紹介していきます!
そもそも基本的な学習の流れは?
勉強しなきゃ!と思って焦っているかもしれませんが、そもそもどのような順序で学習を進めて仕事獲得に繋げていくかを理解しているでしょうか?
ここを理解せずにイキナリ勉強を始めてしまうと、途中で道を外れてしまったり無駄に遠回りして時間がかかってしまう恐れがあります。
まずはwebデザイナーになるための学習ロードマップを知っておきましょう。
1. デザインの基礎を学ぶ
世に出回っている素敵なデザインは、デザイナー一人ひとりが元から持つセンスじゃなく、ルールや技法を組み合わせて作られています。
主に学ぶべき基礎は以下の3つです。
- 基本デザイン原則:バランス、コントラスト、整列、近接、反復など、レイアウトに関すること。
- 色彩理論:色の基本、カラーホイール、補色、類似色、トライアドなど色の使い方や組み合わせに関すること。
- タイポグラフィ:フォントの種類、文字組み、行間、字間、読みやすさなど、文章の作成や表記に関すること。
この時点ではまだ全てを完璧に覚えられなくても問題ありません。「こんな方法があるんだなぁ」と、ザッとでも良いので一通り知ることが大切です。
2.デザインソフトの操作を覚える
こちらもデザイナーにとってはとても大事な部分、実際にデザイン作成に使用するソフトの操作方法の習得をしていきましょう。
デザインソフトは、有名なAdobe社のものをはじめデザイン初心者でも扱いやすいCanvaやfigmaなど幅広く存在しています。
一度に複数のソフトを覚えようとするのは学習効率が悪いので、自信が今後どのジャンルのデザインをメインに手掛けたいか考え、そのジャンルと相性の良いソフトから覚えていくのがオススメです。
主なデザインソフトと、相性の良いデザインの組み合わせは以下を参考にしてみてください。
| Adobe Photoshop | 画像編集、バナーやLPなどweb系メインのデザイン作成 |
|---|---|
| Adobe Illustrator | 名刺、チラシ、イラスト、ロゴなど、印刷物やマーク作成 |
| Canva | web系のデザインやスライド資料などホワイトペーパー作成 |
| figma | webサイトやLPのデザイン作成 |
3. デザインの模写と自主制作でスキルを磨く
デザインの知識とソフト操作の方法をある程度頭に入れたら、実際にデザインを作って練習していきます。
最初のうちは完成されたデザインをweb上から拾ってきて、それを模写してみましょう。既にあるデザインがどう作られているのかよく観察しながら真似をしていくことで、自然とスキルも上達していきます。
ただし、模写をずっと続けるだけではスキルが身につかないので、5〜6個作ったら自主制作(自分で架空の企業や店舗を考えてオリジナルのデザイン制作物を作る、SNS等で配布されているお題をもとにデザインを作るなど)に切り替えましょう。
デザイン制作させてくれそうな知人に声をかけて作らせてもらうのも、実際の案件請負の流れに近い体験ができるのでオススメですよ。
4. 案件応募のためにポートフォリオを作る
自主制作の数が10個程になったら、いよいよポートフォリオ作りです。
ポートフォリオは簡単に言うと、自分の実力を知ってもらうためのデザインカタログの様なもの。
このポートフォリオがしっかり作り込まれていると案件に採用してもらいやすくなる他、いざ作成したら「コチラが求めているレベルと違うから、やっぱり契約はナシで…」といった依頼者側が想定しているレベル感との相違やトラブルなどが起こりにくくなります。
ポートフォリオの作り方はいろいろありますが、今はポートフォリオ作成に特化した無料のサイト作成ツールが多数あるので、それらを利用して見やすいポートフォリオを作っていきましょう。
5. 案件応募や営業をかけて実務経験を積む
ポートフォリオが完成したら、それを持ってクラウドソーシング利用や営業をかけるなどして実案件の獲得を目指していきます。
仕事の探し方は、クラウドワークスやココナラなどのクラウドソーシングサイトやSNS上での募集、デザイン制作会社へ直接DMなどをして営業をかけるなど様々ですので、自分にあった方法で探していきましょう。
自分にあった探し方が分からない方は、以下の記事も参考にしてみてください。
学習にかけられる費用で選択肢が変わる
デザインの基礎やソフトの操作方法を学ぶ手段もさまざま。
今や基礎的なことはYouTubeやブログ等で公開されていることが多く、ネットで調べれば無料で手軽に学べますし、オンラインスクールなども充実しています。
どの手段を利用していくかは自分の好みもありますが、何よりも学習にかけられる費用によって選択肢の幅が大きく変わってきます。
大きく分けて、以下の3つに分類できます。
- 0〜数万円:独学
- 10〜20万円前後:フリーランスデザイナーのコーチングやコンサルサービス
- 50万以上:スクール
ちなみに私は3つとも一通り経験しましたが、自分に合っていたのはオンラインスクールでした。
私は自分1人だとどうしても3日坊主で終わってしまうので、多くの人と一緒に切磋琢磨できるスクールの方がヤル気が継続できて良かったです。
では、それぞれの勉強法がどんな人に向いているのか?
自身の体験から感じた向き不向きのタイプをお伝えしていきます。
出来るだけ費用をかけたくないなら独学で頑張る!
とにかく費用をかけたくない!という人は、独学で学習していくのが一番低コストとなりオススメです。
インターネットで検索すれば、WEBデザインについて学べるYouTubeチャンネルやブログ記事などが無料〜数万円程度の買い切り価格で転がっているので、これらを活用していって仕事が受注できる程度のスキルを身につけることも可能です。
オススメ独学ツール
【無料(YouTube)】
【有料(Udemy)】
しかし、いくら低コストで学習できるとはいえ独学には向き不向きがあります。
「お金がもったいないから」という理由だけで独学を選んでしまうと、スキルが身に付かず時間だけを浪費してしまう恐れも。
そのため、自分が独学でもやっていけるタイプかどうかを事前に知っておきましょう。
独学でもやっていける人の特徴
独学でもやっていける人のポイントは、以下の4つです。
- 自己管理ができる
- 自発的に学ぶ意欲がある
- 問題解決力がある
- 集中力が持続する
1つずつ詳しく解説していきます。
自己管理ができる
独学の場合、自分で「いつどの時間帯に何をするのか」という学習スケジュールを立てて計画的に進めていかなくてはいけません。
また、決めたスケジュールを守らなくても誰かに咎められることがないので、体調不良や他のことで忙しくなって学習期間が空いてしまうと、そのままやらずに挫折してしまうことも。
そのため、常に自分のモチベーションや健康状態を保ち、自分を律しながら学習を続けられるかも大事になります。
自発的に学ぶ意欲がある
先ほどの自己管理に近い部分がありますが、新しいことに対して興味を持って自分から進んで情報を収集し学ぶ意欲がある人の方が学習が続きやすいですしスキルも上達します。
スクールなどと違ってwebデザインの1〜10までがセットになっているわけではなく、学びたい分野や項目ごとに教材や情報を探してくることになるので、自発的に教材を見つけてこないとスキルの量も質も少ないものとなってしまいます。
問題解決力がある
学習中に直面する問題や疑問点を、自分で調べて解決できる力が必要になってきます。
SNSやコミュニティを活用するなど、自分で情報を収集しながら解決策を見つけていかなくてはいけないので、リサーチ力や疑問点を言語化する力もいるでしょう。
集中力が持続する
一人で長時間集中して作業することが苦にならない人も独学に向いています。
人によっては隙間時間を利用しながら学習することもあるでしょうが、自宅やカフェなど自分が集中できる環境を作り、学習すると決めた時間内は必ず集中して取り組むことができればOKです。
特徴に当てはまらない人は他の選択肢も考えてみよう
上記4つのポイントを紹介しましたが、あなたはどうだったでしょうか?
もしも
- 自己管理が苦手
- あらかじめスケジュールや学ぶ内容を決めてもらっていた方が続けやすい
と感じたならば、いくら低コストとは言え独学で学ぶのは一度考えた方が良いかもしれません。
スクールやコンサルティングなど他者と関わりながら学んで行った方が、お金はかかりますが効率的に学べ、その後のデザイン案件で元を取れる可能性が高いですよ。
現役の先輩デザイナーから学べるコンサルサービス
次は、現役で活躍しているフリーランスデザイナーの方が講師となって教えてくれるコンサルサービスや小規模スクールに入って学ぶ方法です。
多くのデザイナーがSNSなどでサービス紹介をしているので、投稿内容を見ながら、自分の目指したい姿や興味のある世界観を持っている人を選ぶと良いでしょう。
私は実際にコンサルメインのサービスを利用したのですが、その時に感じたメリットとデメリットをご紹介していきます。
コンサルサービスのメリット
- マンツーマンで見てくれる
フリーランスデザイナーのコーチングやコンサルは、個々の学習ペースやレベルに合わせて指導をしてもらえます。自分が苦手な部分やわからない点が出てきたら、その都度チャット等で聞いて教えてもらえたため、途中で止まることなく学習を進められました。 - 実践的なアドバイスが得られる
フリーランスデザイナーとして一線で活躍しているプロから、リアルな業界の知識や実務に役立つアドバイスを直接受けられました。そのため、実際に自分で仕事を受注した時も相談等をしながら安心して仕事に取り組めました。 - フィードバックがもらえる
自分のデザインに対して、プロから具体的なフィードバックをもらえます。どこを改善すれば良いのか、どのようにクオリティを上げるかを具体的に教えてもらえるため、自分のデザインスキルが飛躍的に向上します。 - ネットワークが広がる
フリーランスデザイナーとのコネクションを持つことで業界内でのネットワークが広がり、将来的な仕事の機会や協業の可能性が増えます。実際に私も、コンサルサービスを卒業した半年後くらいに講師だったデザイナーさんから仕事を振っていただきました!
コンサルサービスのデメリット
- 費用がかかる
フリーランスデザイナーのコーチングやコンサルサービスは当然有料です。
特に経験豊富なデザイナーのサービスは高額になることが多く、大手のデザインスクールと変わらない金額になってしまう場合もあります。 - 相性の問題
事前に情報を見て「この人良さそう!」と思っても、実際にコーチングやコンサルを受けてみたら相性が合わないということもあり得ます。相性が良くないまま学習を進めてもストレスを感じたりスキルが上達しにく苦なってしまいます。
- スケジュールの調整が必要
講師に質問したりデザイン指導してもらう際、お互いのスケジュール調整が必要になります。
なかなか時間が合わないと学習のペースが遅れてしまうので、余裕を持ったスケジュールが組める人じゃないとストレスに感じるかもしれません。 - 自己学習の習慣が身につかない可能性がある
コーチやコンサルに依存しすぎると、自己学習の習慣が身につかない可能性があります。
講師にすぐ聞けるのはフリーランスデザイナーのコンサルの良い点ですが、その環境に慣れすぎてしまうと独り立ちした時に困ってしまうので注意が必要です。
デザイン以外のスキルも複合的に学べるスクール
最後はデザインスクールです。スクールには通いのタイプとオンライン受講できるタイプの2種ありますが、基本的にオンラインの方が時間の融通がきいてスクール数も多いので、ここではオンラインスクールについて話していきます。
オンラインデザインスクールのメリット
- 体系的なカリキュラムが組まれていて学びやすい
ほとんどのスクールでは、初心者から上級者まで体系的に学べるカリキュラムが整っています。
基礎から応用までを一貫した流れで学べるため、初心者でも無理なく段階的にスキルを習得することができます。 - 専門的な指導を受けられる
プロのデザイナーや経験豊富な講師から直接指導を受けられるため、最新のデザイン技術や業界のトレンドを学べます。カリキュラムとは別で受講生限定のセミナーや講義が行われるスクールも多いので、常に最新の情報に触れられますよ。
- 実践的な課題がある
多くのデザインスクールでは、実際にある仕事に基づいた課題が出されます。
この課題をこなしていくことで実務に近い環境でスキルを磨くことができ、卒業後の仕事獲得にも役立ちます。 - 同じ志を持つ受講生たちと交流できる
同じ目標を持つ仲間と出会い、情報交換を行う場が設けられていることが多いです。そのためデザイナーのネットワークを築くことができ、将来の仕事受注や協業の機会に繋がることもあります。
オンラインデザインスクールのデメリット
- 高額な費用がかかる
デザインスクールは一般的に高額な授業料がかかります。特に有名なスクールや専門的なコースでは学費が高くなる傾向があり、資金の余裕がないと受講がしづらいです。
- 学習期間の拘束がある
受講する際に、学習できる期間が決められている場合がほとんどです。
そのため、受講期間が過ぎてしまうと学習カリキュラムが一切見れなくなってしまう恐れがあります。 - カリキュラムが固定化されている
デザインスクールのカリキュラムは基本的に固定されているため、受講したコースに学びたいと思っていた項目がなかったり、途中で新しく気になった分野が出てきても学べません。
追加で費用を払って新しいコースを受講する必要が出てきてしまいます。
おすすめのデザインスクール3選
オンラインのデザインスクールを探してみると色々と出てくるので、どのスクールが良いのか分からず選べない人も多いのではないでしょうか?
そこで、私が体験等を通じて良いと感じたスクールを3つ紹介していきます。
ぬるま湯デザイン塾

| 詳細内容 | |
| 受講期間 | 12週間(約3か月)200時間 |
| 特徴 |
|
| 講師 | 現役のWEBデザイナー |
| 料金(受講料) | 348,000円(税込)※無料セミナー参加者 |
| 公式サイト | https://l-works.design/ |
ぬるま湯デザイン塾は、90日間の学習でWEBデザイナーを目指すことができるオンラインスクールです。
webデザインに特化していますが、時期によってSNSやグラフィックデザインの講座なども開いているので、デザインを幅広く学びたい人にはオススメです。
また、受講生1人1人に担当講師がついて講師と二人三脚で学習を進められるので、学習についていけるか不安な人も安心して受講できます。
なお、ぬるま湯デザイン塾の受講料は無料セミナー経由で契約すると34万8,000円(税込)、無料セミナーを受講せずに契約すると39万8,000円(税込)となるので、受講を考えている人は必ず無料セミナーを受けてから契約しましょう。
日本デザインスクール

| 詳細内容 | |
| 受講期間 | 45日間 |
| 特徴 |
|
| 講師 | 現役のWEBデザイナー |
| 料金(受講料) | 649,990円 |
| 公式サイト | https://l-works.design/ |
45日間でプロ並みのスキルを習得できるカリキュラムで、時間に制限がある会社勤めの人や主婦の方でも効率的にWebデザインを学べます。
また、実務に沿った課題がある上に講師から添削してもらえるので、実務に役立つデザインスキルを身につけていくことが可能です。
こちらも無料の体験セミナーやYouTubeチャンネルで受講者の声を公開しているので、スクールの雰囲気を知りたい人はぜひ観てみてください。
SHElikes(シーライクス)

| 詳細内容 | |
| 受講期間 | 1ヶ月〜 |
| 特徴 |
|
| 講師 | 目標とするキャリアを実現している女性講師 |
| 料金(受講料) | 13,567円〜(別途入会料:162,800円) |
| 公式サイト | https://shelikes.jp/ |
SHElikesは、目標とするキャリアを実現している女性講師からWebデザインを学べる、女性限定のオンラインスクールです。
webデザインを中心に、ライティングや動画編集、フリーランスとして必要になってくるビジネススキルなど幅広く学べるので、デザイン以外も興味がある人にはピッタリです。
数多くのメディアにも取り上げられているほど人気も認知度も高いのも安心できるポイントです。
番外編:リモラボ

| 詳細内容 | |
| 受講期間 | 1ヶ月〜 |
| 特徴 |
|
| 講師 | 目標とするキャリアを実現している女性講師 |
| 料金(受講料) | 税込21,780円(別途入会料:税込198,000円) |
| 公式サイト | https://lp.remolabo.jp/ |
こちらのリモラボはデザインスクールではないのですが、在宅ワークを目指す女性に向けてリモートワークスキルやSNS運用スキルを中心にデザインやマーケティングなど幅広く学べるスクールです。
webデザインの中でもSNS運用に特化しているスクールなので、SNS運用代行に興味がある人や自身のSNSを運用してデザインの仕事を獲得していきたいと考えている人にオススメ。
また、リモラボ独自のコミュニティサイト&アプリの「リモシティ」というものがあり、受講生をはじめ講師陣とも交流ができるので、オンライン特有の孤独感を感じることなく、仲間と一緒に切磋琢磨できるのもポイントです。
自分にあった学び方で効率よくスキルを身につけよう!
今回はwebデザインを学ぶ方法と流れをご紹介しました。
主にデザインを学ぶ方法は費用別に以下の3つに分けられます。
- 費用0〜数万円:独学
- 費用10〜20万円前後:フリーランスデザイナーのコーチングやコンサルサービス
- 費用50万以上:スクール
それぞれにメリットデメリットがあるので、学習にかけられる費用と自分の性格の両方を加味して最適な学習方法を選んでスキルを身につけていきましょう。